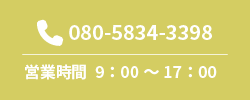📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第2回
最初のステップ「リースの識別」
リースの会計処理は、契約が「リースかどうか」の判断から始まります。ここでの見落としは、オンバランスすべき資産および負債の計上漏れにつながり、適用直前での関係者への説明及び修正対応等を強いられるリスクを生じさせます。
その意味において、「リースの識別」は極めて重要です。
契約書に「リース契約書」と書かれているかどうかではなく、契約(書面の有無は無関係)に基準が定義する「リース」が含まれているかどうかが重要です。
リースの識別
契約当事者は、契約がリースを含むか否かを、次の2点を考慮して判断する必要があります。
✅契約において特定された資産があるか?
✅借手がその資産の使用を支配しているか?
この2つをいずれも満たす契約はリースに該当し、原則として使用権資産およびリース負債の認識が求められます。(「原則として」→リースのうち少額リース及び短期リースについてオンバランスしない可能性があります。→第5回で解説予定です)
🟦① 特定された資産があるか
📌 感覚的な表現になりますが、
「このロケーション(ここ!)」「この設備(これ!)」と具体的に👉指をさすことができる他社所有の資産かどうかです。
たとえば、倉庫内の100㎡を借りているものの、使用場所をサプライヤーが都度自由に決められる(先ほどの例に対応させると👉指先が動かない)契約における資産は、「特定された資産」とは見なされない可能性があります。
一方で、契約書に添付された見取図などにより使用場所が特定されており、かつサプライヤーが一方的に変更できない契約(👉指先が動く)であれば、「特定された資産」に該当する可能性が高まります。
🟦② 使用を支配しているか
📌 判断における実務的な感覚としては、
その資産を使って得られる利益は自分のものであり、かつ資産の使い方を自分で決められるかどうかです。
→ 所有権のない他社の資産をあたかも自己の所有物のように使える状況です。所有権のある資産はもともとオンバランスされていますので検討する必要はありません。
ここでのポイントは、「誰がどう使うかを決めるか」「使って得られるメリットが誰のものか」という2点にあります。
フローチャートと設例の活用
リースか否かの判断に迷う契約については、新基準の適用指針の設例に付されたフローチャートと、関連する適用指針の記載を踏まえ、監査法人との事前合意を取ることが望まれます。
出典:企業会計基準委員会
「リースに関する会計基準の適用指針の設例」【設例1】リースの識別に関するフローチャート
経理部門と現場部門における具体的な手順
(1) 経理部門でのリースの識別
✅勘定科目単位で定期的な支払いがある取引を抽出
✅契約書をレビューしてリースの有無を判断
✅現在リース処理している契約も再確認(補助的ではあるが有用)
(2) 現場部門主導でのリースの識別(いわゆる「隠れリース」(※))
✅経理部門で実務感覚に即した質問書を作成(基準文言だけですと意図が伝わらないリスク)
✅製造原価に計上される契約を中心に確認してもらう
こうした手順を経ることで、見落とされがちな“隠れリース”も体系的に洗い出すことが可能になります。
※ 隠れリースについて、10回シリーズとは別の稿でまとめる予定です。
契約書のタイトルに「リース」の文字がなく、「業務委託契約」「販売委託契約」「物品貸与契約」などの名称であっても、特定された資産の使用を借手が支配していれば、それはリースです。
契約の名称は大切ですが、その内容と実質がより重要です。
現行のリース取引会計基準との違い
現行基準では、実質的に解約不能なリース契約について、現在価値基準および経済的耐用年数基準など、形式的な数値条件に基づいて資産計上の対象を決定しています。
新基準では、まず契約がリースに該当するかどうかを、数値基準を含まない実質判断のフローに従って評価し、該当するものは原則オンバランス処理されます。
基準の名称の違いに着目してください。現行基準(旧基準)には「取引」の文字が含まれていますが、新基準には含まれていません。旧基準は、リース料の支払いが均等であるような典型的なリース取引と不動産リースのみが対象とされていますが(📖リース取引に関する会計基準の適用指針)、新基準ではそのような限定が付されておらず、実質的な検討を求められることが示唆されています。
まとめ
新リース会計の第一歩は、「この契約にリースが含まれるか?」というリースの識別です。
そのためには、資産が明確に特定されており、かつ使用から得られる経済的利益が借手に帰属するかどうかという契約の実態を丁寧に見極める必要があります。
次回は、「リース期間はどこまで含めるべきか?」というテーマを扱います。
延長・解約のオプション、合理的に確実の考え方など、判断が分かれやすいポイントを整理して解説します。
📌 次回予告:「リース期間」の見極め方(2025年7月4日投稿予定)
この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。
内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。