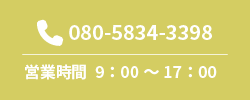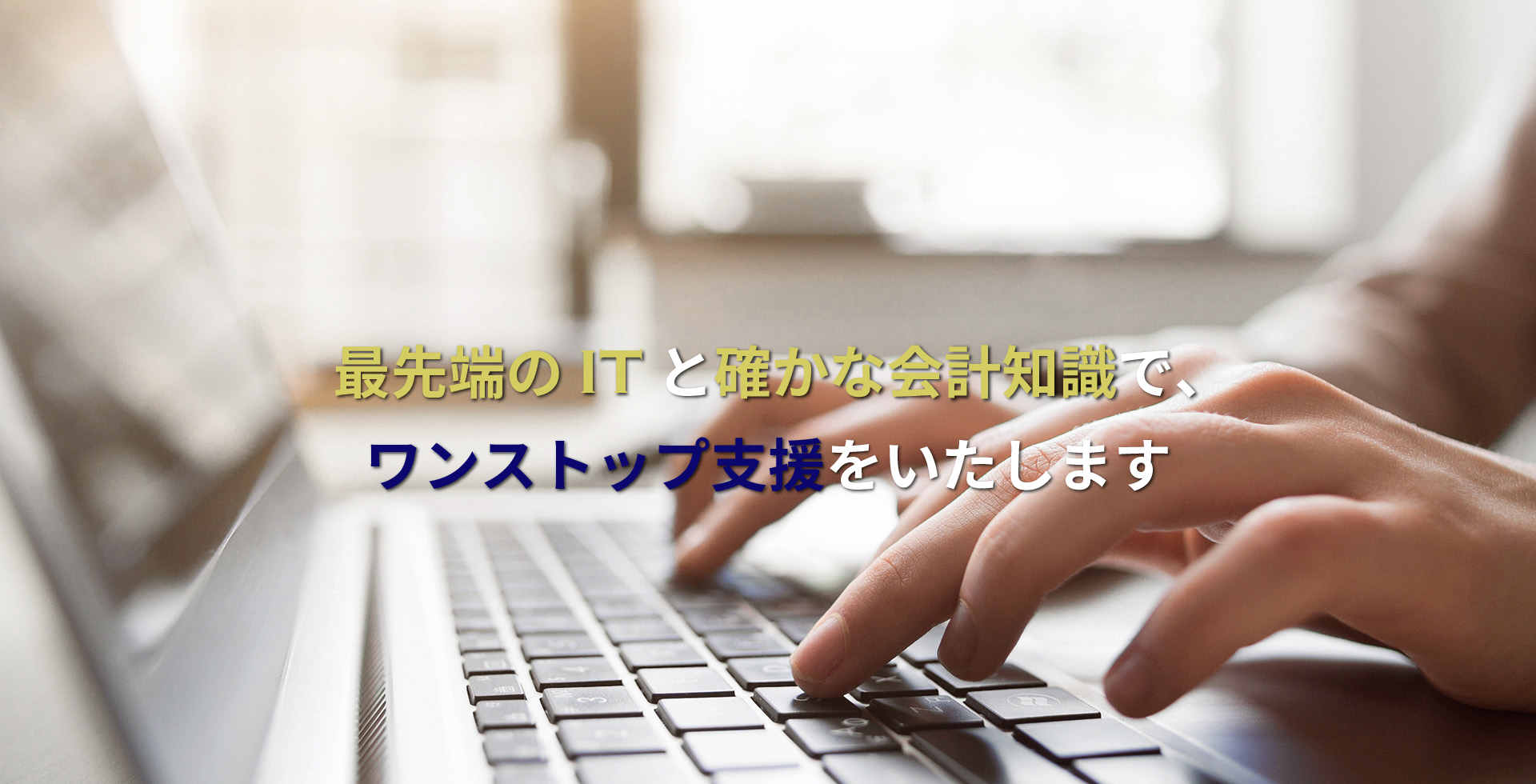📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第6回
リース期間中の会計処理をどうするか?
こんにちは。今回は、リース期間中に借手が行う会計処理について、実務の視点から解説します。ポイントは、次の3点です。
- リース負債の「利息」と「元本返済」への配分
- 使用権資産の減価償却
- 減損の検討
本編では、第4回と同じ設例を用いながら、現場で迷いやすい論点を具体的に取り上げます。
リース負債の処理:利息と元本の配分
最初にリース負債の会計処理を取り上げます。リース負債は、毎月のリース料を支払うことで徐々に減っていきます。ただし、支払額すべてが負債の返済に充てられるわけではありません。
支払額の中には、利息相当額も含まれているため、「利息」と「元本返済」に分ける処理(利息法による配分)が必要です。
第4回の設例を使用します。
- リース負債の初回認識額:5,000,000円
- 支払回数:36回(3年間)
- 支払方法:月初払い
- 金利:年3.5%
- 月額リース料:146,084円(最終月のみ146,095円)
返済スケジュール(抜粋)
| 月 | 支払額(円) | 利息(円) | 元本返済(円) | 期末残高(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 146,084 | 0 | 146,084 | 4,853,916 |
| 2 | 146,084 | 14,139 | 131,945 | 4,721,971 |
| 3 | 146,084 | 13,764 | 132,320 | 4,589,651 |
| … | … | … | … | … |
| 36 | 146,095 | 423 | 145,672 | 0 |
仕訳例(月次)
- 月初支払時:
(借)リース債務 131,945
(借)支払利息 14,139
(貸)現金預金 146,084
使用権資産の減価償却
続いて、使用権資産の減価償却を取り上げます。リース期間にわたり、使用権資産についても減価償却を行います。
この例では、初回認識時に5,000,000円の使用権資産を計上しているため、これをリース期間(36か月)で定額償却すると、1か月あたりの償却費は以下のとおりです。
- 月額償却費:5,000,000 ÷ 36 = 138,889円(1円単位四捨五入)
仕訳例(月次)
- 月末に償却費を計上:
(借)減価償却費 138,889
(貸)使用権資産 138,889
使用権資産の減損
減損の兆候にあたる場合において、他の固定資産と同様に、減損会計の適用対象となります。
減価償却の区分とその判定基準
使用権資産の減価償却期間と方法は、次の2つのパターンに分かれます。
(1)リース期間終了時に資産の所有権が移転すると認められるリース
・耐用年数:資産の経済的耐用年数
・減価償却方法:当該資産の種類に応じた方法
(2)それ以外のリース
・耐用年数:リース期間
・減価償却方法:企業の会計方針に従う(実務上は定額法が一般的)
判定ポイント
以下のいずれかに該当する場合には、所有権が移転すると認められます。
・リース期間終了時に資産を譲渡することが契約上明らかである
・極めて低額な金額で資産を譲渡する選択権(旧基準における割安購入選択権に相当)が借手に与えられている
・借手が当該資産を専用の仕様に変更して使用しており、他の用途に使用できないと認められる
※これらの要件は、旧基準における所有権移転ファイナンス・リースの判定方法を実質的に引き継いでいます。
契約変更時の再測定
最期に契約変更時の取扱いです。リース期間やリース料の変更など、契約変更があった場合には、リース負債の再測定が必要となることがあります。変更内容に応じて、使用権資産の帳簿価額も調整されます。
補足:借地権の設定にかかる権利金等の減価償却
借地契約に伴い支出される権利金等が、リースの対価として支出されたと認められる場合には、使用権資産として資産計上され、借地契約期間等にわたり定額法などで償却されます。
ただし、保証金的な性格を持つ支出や、リースに該当しないと判断される場合には、使用権資産には含まれません。
📅 次回予告:第7回:貸手の会計処理の全体像
👉 投稿予定:2025年8月29日
貸手の会計処理は旧基準からの変更点は少ないとされますが、実は見落と
この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。
内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。