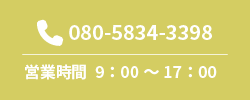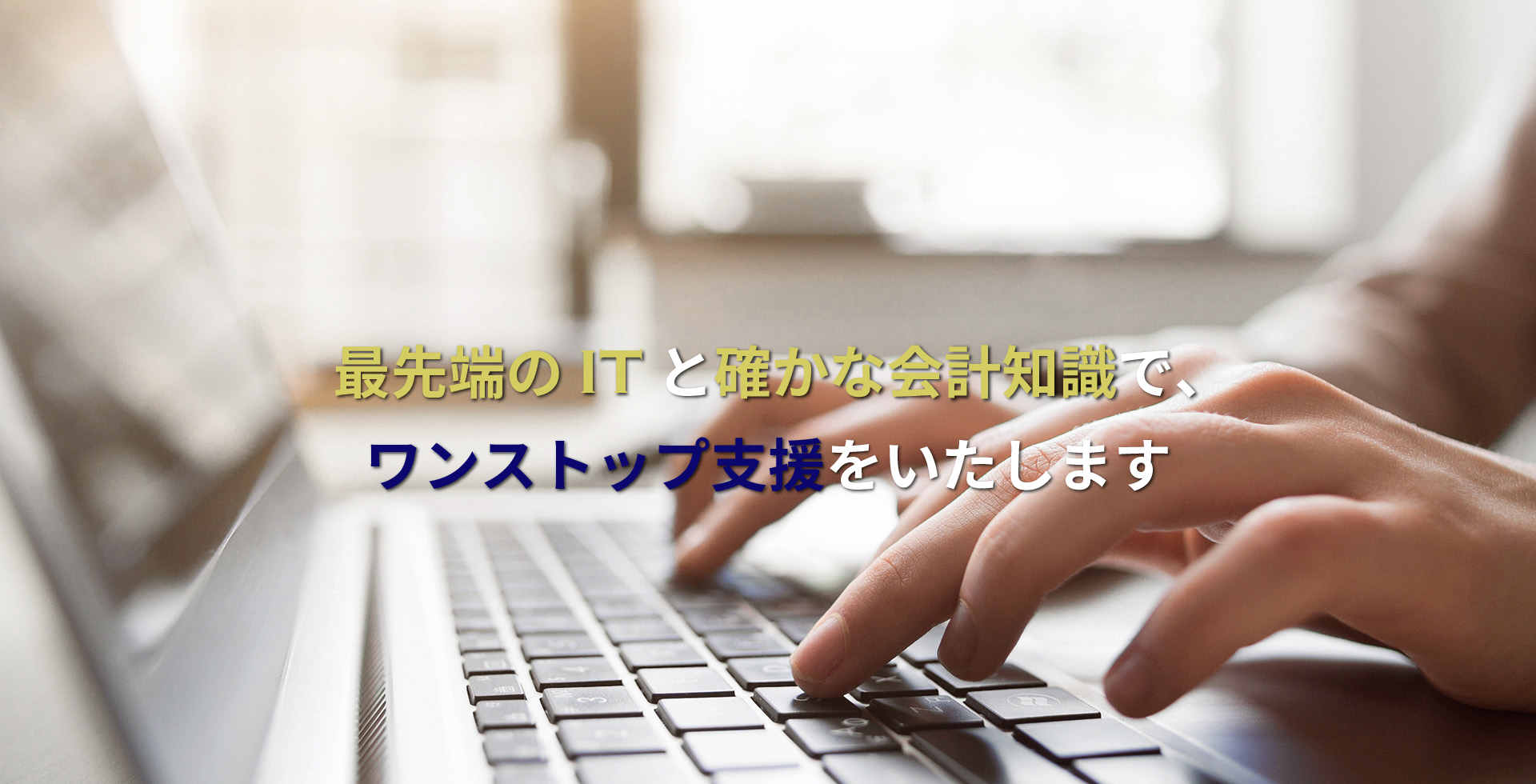📘新リース会計基準 実務解説シリーズ 第5回
例外の取り扱い ―「短期リース」と「少額リース」―
リース会計基準では、すべてのリースを資産・負債として認識するのが原則ですが、実務負担や費用対効果を踏まえ、一定のリース契約については会計処理の例外が認められています。それが「短期リース」と「少額リース」です。今回は、この2つの例外規定について、実務上の判断ポイントを紹介します。
2つの例外
借手は、以下の2つの条件を満たすリース契約について、オンバランス処理を行わずに費用処理することが認められます(リース会計基準22項)。
- 短期リース(リース期間12か月以内で買い取りオプションなし)
- 少額リース(資産ごとの価額が少額であるもの)
短期リースの取扱い
✔ 定義
- リース期間が12か月以下
- 延長オプションがないこと
✔ 実務的ポイント
- 短期リースに該当する場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができます。
- 契約期間が10か月でも、延長オプションがある場合は短期リースに該当しません。
少額リースの取扱い
次の(1)と(2)のいずれかを満たす場合に、短期リースと同様に、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができます。(2)は①と②のいずれかを首尾一貫して選択適用します。
(1) 重要性が乏しい減価償却資産について、購入時に費用処理する方法が採用されている場合で、借手のリース料が当該基準額以下のリース
この基準額は、通常取引される単位ごとに適用し、リース契約に複数の単位の原資産が含まれる場合、原資産の単位ごとに適用することができます。
(2) 次の①又は②を満たすリース
① 企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースで、かつ、リース契約1 件当たりの金額に重要性が乏しいリース(※)
この場合、1 つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれているときは、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができます。
② 新品時の原資産の価値が少額であるリース
この場合、リース1 件ごとにこの方法を適用するか否かを選択できます。
(※)BC43項において、旧基準における300万円基準の判定方法を踏襲することを目的としたものである旨が規定されています。
🔷 実務上の具体例(PCリース契約のケース)
- PC20台のリース(リース期間3年)
- 1台あたり新品時価格:13万円(税抜)+利息相当額1.3万円
- 維持管理費:上記と別に1台あたり1万円(利息含め1.1万円)
- 事業内容に照らして重要性が乏しいリースとします
→したがって、リース料総額=((13+1.3)+1.1)*20台=308万円となり、この段階で契約単位で300万円を超えています。
(1)の判定 (判定1)
減価償却資産の基準額を10万円としている場合、利息相当額だけ高めに基準額を設定することが認められています(この事例では11万円とします)。
1台当たり 14.3万円 > 11万円
(2)①の判定(判定2①)
事業内容に照らして重要性が乏しいものの、リース契約1件当たりの重要性が次の通り乏しいとは言えない。
リース契約単位(維持管理費用相当額を除外可)で14.3万円*20台=286万円 < 300万円
(2)②の判定(判定2②)
1台当たりの新品時価格 13万円 < 5,000ドル(BC41項で例示)
(2)①を適用する企業の判定
判定1は基準額を超えていますが、判定2①は維持管理費用相当額を除外した契約額が300万円を下回ることから少額リースに該当します。判定1と判定2①のいずれかが該当すれば良いためです。
(2)②を適用する企業の判定
判定1は基準額を超えていますが、判定2②は1台当たりの新品時価格が基準額を下回ることから少額リースに該当します。判定1と判定②のいずれかが該当すれば良いためです。
短期リースの注記
短期リースについては、費用発生額が含まれる科目及び発生額を注記する必要があります。
ただし、借手のリース期間が1か月以下のリースにかかる費用を含める必要はありません。
一方で、少額リースについては注記の対象外です。
📅 次回予告:第6回:リース期間中の会計処理をどうするか?
👉 投稿予定:2025年8月5日
利息の配分及び減価償却の取り扱いなど、リース期間中の会計処理に焦点を当てて解説します。
この記事は、公認会計士・石谷敦生が執筆しています。
内容はすべて筆者個人の見解に基づくものであり、いかなる団体や第三者の意見を代表するものではありません。